運送業界の人手不足が叫ばれて久しい。政府もメディアも「待遇改善」「働き方改革」と声を揃えているが、果たしてそれだけで解決する問題だろうか? 現場に身を置く者として、もっと根本的な視点が必要だと感じている。それは、「人と人のつながり」の軽視がもたらした弊害だ。
たしかに長時間労働や低賃金は大きな問題だ。しかし、もう一歩踏み込んで考えてみてほしい。なぜそれほどまでに過酷な状況が長年放置されてきたのか? それは、“現場の声”が届いていなかったからではないか。経営層と現場、元請けと下請け、ドライバーと配車係――その間に「対話」がなくなり、「信頼関係」が薄れていたのではないだろうか。
人手不足の現状を見ると、多くの若手が入ってこない理由は「仕事がきつそうだから」だけではなく、「人間関係が閉鎖的」「相談しづらい」「孤立しやすい」といった、精神的なハードルも大きい。実際、SNSで「運送業界にはもう戻りたくない」と語る元ドライバーの声は少なくない。つまり、待遇を上げるだけでは人は定着しないということだ。
では、何が必要なのか。まずは現場同士の“顔の見える関係”を取り戻すこと。ドライバー同士が声をかけ合える空気、管理者が現場に足を運び、ただ「指示する」ではなく「話を聞く」姿勢を持つこと。こうした小さな積み重ねが、職場の雰囲気を変え、長期的な人材定着につながる。
また、元請け・下請けの間で「人を使い捨てにする感覚」がまだ残っている現場もある。過剰な納期や低単価の仕事が現場を疲弊させ、人材が逃げるという悪循環に拍車をかけている。効率を追うあまり、人間関係の“余白”を失っていないか? 今一度、現場の在り方を見直す時ではないか。
「人手が足りない」のではない。人が“続かない”職場を作ってしまっている、それが現実だ。本当の意味で人材を確保するには、待遇改善に加えて、「人を大事にする文化づくり」が不可欠だ。物流の要を支えるのは、AIでもロボットでもない。“人”だという原点を、私たちはもう一度思い出す必要がある。
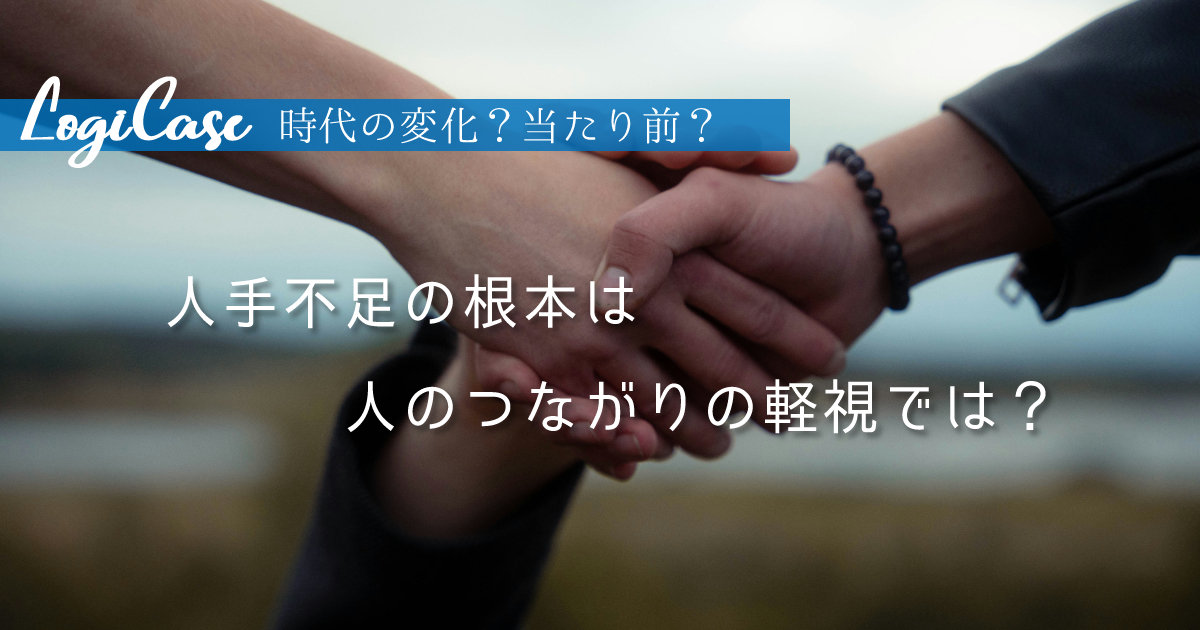
コメント