「何を言っても言うことを聞かない」
「自分の好き勝手な行動ばかりする」
「チームの和を乱す存在になっている」
そんな“わがままな社員”に、頭を抱えている管理職の方は多いのではないでしょうか。
彼らの態度にストレスを感じつつも、「注意すれば逆ギレされる」「退職されたら困る」「そもそも何を言っても響かない」と感じ、結局放置してしまっていませんか?
その結果、職場にはモヤモヤが蔓延し、他の社員のやる気にも悪影響が広がっていきます。
でも、ここでひとつ厳しい現実をお伝えします。
「わがままな社員」は、勝手に育つわけではない。
彼らをそこまで“育ててしまった”のは、管理職であるあなた自身の関わり方にも責任があるのです。
自分のマネジメントを省みることなく、ただ「部下が悪い」と責任を押し付けていては、問題は何一つ解決しません。
本記事では、「なぜ社員はわがままになるのか」という根本原因から、今からでも遅くない具体的な対処法、そして再発防止のための環境づくりまでを、徹底的に掘り下げていきます。
なぜ、社員は「わがまま」になるのか?
社員がわがままになる理由は、本人の性格だけでは語れません。
環境、教育、対応──そのすべてが絡み合って「モンスター社員」が生まれるのです。
1. 注意されない環境=やりたい放題
「面倒だから」「反発されたくないから」と注意を避けていると、それは本人にとって「黙認された」というサインになります。
例:
ある社員が遅刻を繰り返しているが、管理職が「またか」と黙認していたところ、遅刻は常習化。やがて他の社員も「別に遅刻しても怒られないんだ」と感じ始め、職場全体のモラルが崩壊した──というケースは珍しくありません。
2. 成果さえ出せば何でもアリという誤った評価
営業成績が良い、技術力がある…そのような理由で、ルール違反や他者への迷惑行為を見逃していませんか?
**結果主義が度を超えると、「チーム」ではなく「個人勝手主義」**がはびこります。
3. 一貫性のないルール・態度
「昨日はOKだったのに今日はNG」
「Aさんには注意するのにBさんには甘い」
こういった一貫性のなさは、社員に混乱を与え、「自分のルールで動けばいい」と誤認させます。
「わがまま社員」を生み出したのは、管理者自身かもしれないという現実
少し耳が痛いかもしれませんが、以下のような管理行動をしていませんか?
- 波風を立てたくなくて見て見ぬふりをしていた
- 「まあそのうち変わるだろう」と放置していた
- 一部の社員にだけ甘く接していた
- 明確なルールを提示せず、曖昧な指示で済ませていた
**これらは全て、「わがままを育てるマネジメント」**です。
相手が悪いのではなく、対応しなかったあなたにも問題があるという現実に、まずはしっかり向き合う必要があります。
今すぐできる!現状を打破するための具体的アクション
「今さら遅い」「関係が悪化するのが怖い」と思っている方にこそ、試してほしい打開策を紹介します。
1. 「ルールと期待値」を明文化し、全体に共有せよ
チームとして「何が許され、何がNGか」を明文化していないと、わがまま社員は“解釈の余地”を利用して行動を正当化します。
やるべきこと:
- 業務上のルールや価値観をドキュメント化
- 「この行動は評価される」「この行動は注意対象」と明確に伝える
- Slackやチャット、掲示板などで全体共有
2. 面談・対話を逃げずに実行する
直接対話は避けたくなりますが、ここを避けていては何も変わりません。
まずは1対1で、事実に基づき冷静に伝えることが重要です。
ポイント:
- 感情的に叱るのではなく、客観的な事実に基づいて指摘
- 相手の言い分を一度聞く(ただし言い訳に流されない)
- 改善期限を設ける(「3ヶ月以内に●●できるように」など)
3. 行動変化を記録・評価に反映する
日々の行動や変化を記録しておけば、後で「言った・言わない問題」を避けられます。また、評価に明確に反映することで、“本気度”を相手に伝えることができます。
4. 他の社員の信頼を守るための「厳しさ」を持つ
時に、配置転換や降格、最悪の場合は退職勧告も視野に入れるべきです。
なぜなら、1人のわがままを放置することで、5人、10人のモチベーションが下がるからです。
今後同じことを繰り返さないための「再発防止策」
一度問題を乗り越えても、また同じような社員が出てくる可能性はあります。
そこで重要になるのが「環境整備」です。
● 定期的な個人面談を仕組み化する
半年に一度の評価面談だけでなく、月1の軽い面談を設けることで、日頃の考えや悩み、誤解を早期にキャッチできます。
● 「協調性」や「態度」も評価対象に含める
成果主義も重要ですが、チームで働く以上は態度・姿勢も大切な評価軸です。
360度評価やピアレビューを取り入れるのも有効です。
● 管理職自身のスキルアップを怠らない
問題社員の育成を防ぐためには、管理職自身のマネジメント能力向上が不可欠です。
リーダーシップ、対話力、メンタルマネジメントなど、常にアップデートを意識しましょう。
【最後に】本当に変えるべきは、「相手」ではなく「自分のマネジメント」
わがままな社員を「問題」として切り捨てるのは簡単です。
しかし、それを生み出した環境を見直さない限り、また同じ問題は繰り返されます。
あなた自身が「何を見逃し」「どんな甘さがあったか」を冷静に振り返り、今この瞬間から行動を変えていくこと。
それが、職場を再び前向きな空気に戻す唯一の方法です。
部下を変える前に、自分が変わる。
それが本物の「リーダーシップ」ではないでしょうか?
✅【自己点検】あなたのマネジメントが“わがまま社員”を育てていないか?チェックリスト
以下の項目に1つでも当てはまる場合、あなたの関わり方が“わがままを助長”している可能性があります。
チェックを入れて、自身のマネジメントを客観視してみましょう。
✅問題社員に対し、「また今度言おう」と注意を先送りにしている
✅社員によって指導の厳しさやルールの適用に差がある
✅成果さえ出していれば多少の問題行動には目をつぶっている
✅チーム内で「何が正しい行動か」を明文化していない
✅注意するとき、感情的になって伝えてしまうことがある
✅定期的な1on1やフィードバックの機会が不足している
✅部下の問題行動を「性格だから」と諦めて放置している
✅自分のマネジメントスキルを数年間アップデートしていない
☑3つ以上該当した方は要注意!
改善すべき“関わり方の癖”があるかもしれません。
チェックが多ければ多いほど、今すぐ行動を見直す価値があります。
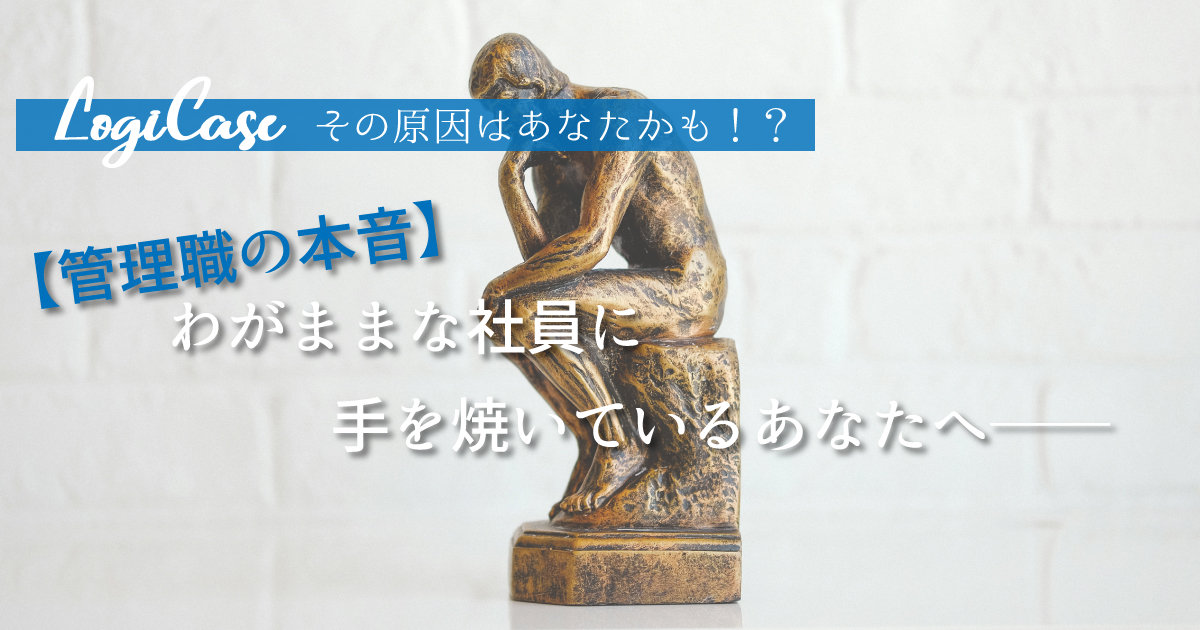
コメント