かつての運送業界は、「荷物さえ運べば儲かる」時代だった。しかし、今はもうそんな幻想は通用しない。働き方改革、2024年問題、そして人材不足。旧態依然としたやり方では生き残れないのが、今の運送業界の現実だ。だからこそ、今こそ“キャッシュフロー”の考え方を叩き直す時が来た。
昔の運送会社はそれでよかった
昭和、平成の時代。トラックが動いてさえいれば金が入った。物流量は右肩上がり、燃料代や人件費も今ほど圧迫感はなく、長時間労働も美徳とされた時代だ。会社は多少ずさんな経営でも、現場の根性と稼働時間で何とかなった。要するに、“気合と根性”で回っていたのである。
だが、それは過去の話だ。令和の時代に入ってから、様々な制限が加わり、現場の負担は増すばかり。古いやり方を貫いている会社ほど、キャッシュが減り、社員は離れ、事業そのものが沈みかけている。
2024年問題で完全にゲームチェンジが起きた
2024年問題──つまり、トラックドライバーの時間外労働の上限規制。この一手で、長時間労働という“非常手段”が封じられた。国が「これ以上働かせるな」と言っているのだ。物流の根幹である“人”が確保できない中、これまでのような働き方はもはや通用しない。
加えて、人件費、燃料費、車両費用、保険、税金……出ていく金ばかりが増えている。利益どころか、現金が回らないという中小運送会社も珍しくない。
つまり、昔ながらの「運んで稼ぐ」だけでは、もはや会社が成り立たない。ドライバーの働き方が変われば、運送会社の経営方針そのものを変えなければならないのだ。
解決策はただ一つ。キャッシュフローを増やせ
「利益率を上げろ」「コスト削減しろ」などとよく言われるが、それは焼け石に水だ。現実的な解決策はキャッシュフロー=“会社に入ってくるお金”を増やすこと、これしかない。
運ぶ荷物の単価は限界がある。値上げ交渉も簡単ではない。つまり、“運送以外”のキャッシュポイントを作ることが、会社を守るために必要不可欠な戦略なのだ。
売上が減っても、キャッシュが潤沢なら倒産しない。逆に、売上が多くてもキャッシュが回らなければ即アウト。それが現代の経営の基本ルールだ。
ネットを活用せよ。情報発信=キャッシュ創出の起点
ここで考えるべきは、「ネットを使ってどう稼ぐか」だ。情報発信を徹底し、自社の存在価値をオンライン上でアピールする。ホームページ、SNS、ブログ、YouTube──これらは単なる広報ツールではない。キャッシュを生む“武器”だ。
例えば、トラックの日常風景をSNSで発信し、人気アカウントに成長させる。そこからグッズ販売や案件紹介、広告収益につなげる。あるいは、会社として物流業界のノウハウをオンライン教材にし、法人向けに販売する。やり方は無限にある。
重要なのは、「自分たちの本業の中にある価値に、ネットという別の回路で価格を付ける」発想だ。
認知度が上がれば、キャッシュの回路が一気に増える
ネットでの情報発信により会社の認知度が上がれば、思わぬところからキャッシュの流入口が増える。求人が集まる、メディアに取り上げられる、スポンサーがつく、企業案件が来る──これらはすべて“会社の露出”が起点だ。
無名の運送会社が、「SNSで話題の会社」となれば、世の中の見る目は一変する。小さな会社でも、発信力があれば、資本力のある大手と対等に渡り合うこともできる。
もたらされる多面的なメリット
この取り組みにより得られるメリットは一つではない。以下に列挙する。
- 求人効果:若手のドライバー志望者はネットで会社を探す。見つけてもらえなければ、応募すら来ない。
- 物販事業:社名入りグッズやトラックモチーフのアパレル、キーホルダー等が売れる時代。ファンが増えれば副収入になる。
- 協力会社の拡大:情報発信により同業の目に止まり、「うちと一緒に仕事しませんか?」という声もかかる。
- 大手企業への営業:ネットでの知名度があれば、大手への商談時も「知ってますよ」と言ってもらえる。これは営業武器として圧倒的だ。
これらは、どれか一つが当たれば成功、という話ではない。複数の収入源を持ち、リスクを分散させる“経営の盾”を持つことが目的だ。
最後に──動かなければ沈む
時代は変わった。現場に“根性”を求める時代は終わった。求められるのは、経営者の“頭の使い方”だ。
運送業という軸はそのままに、ネットを味方にし、新たなキャッシュの回路を作り出す。それこそが、令和の時代を勝ち抜く運送会社の生存戦略だ。
生き残るのは、強い会社ではない。変化に適応した会社だけだ。
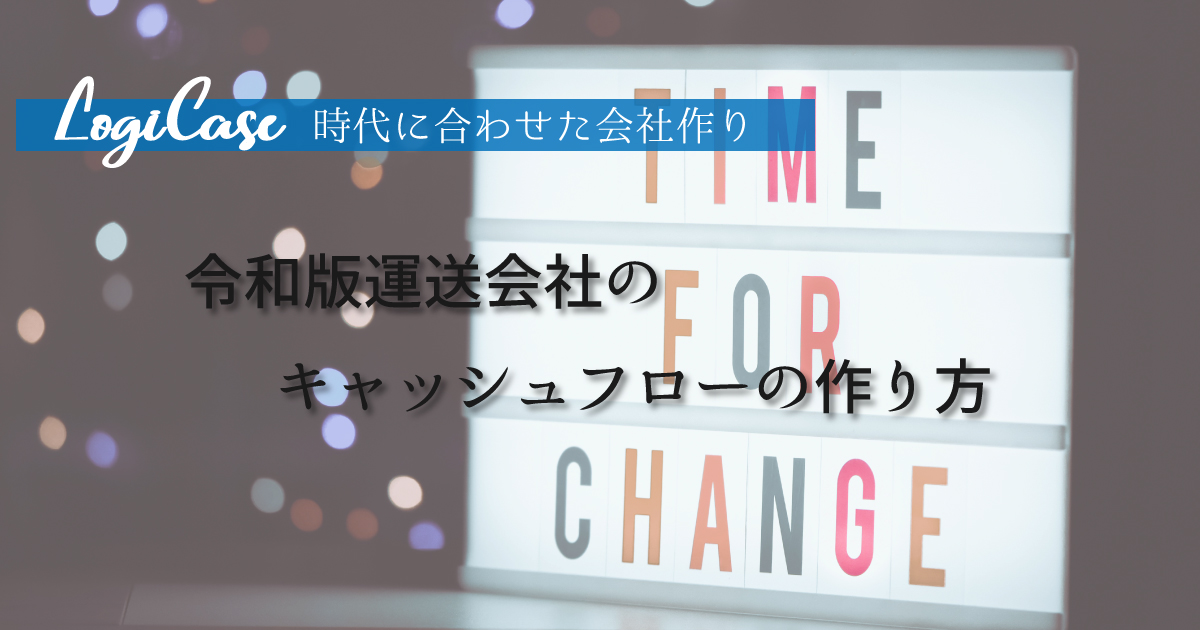
コメント